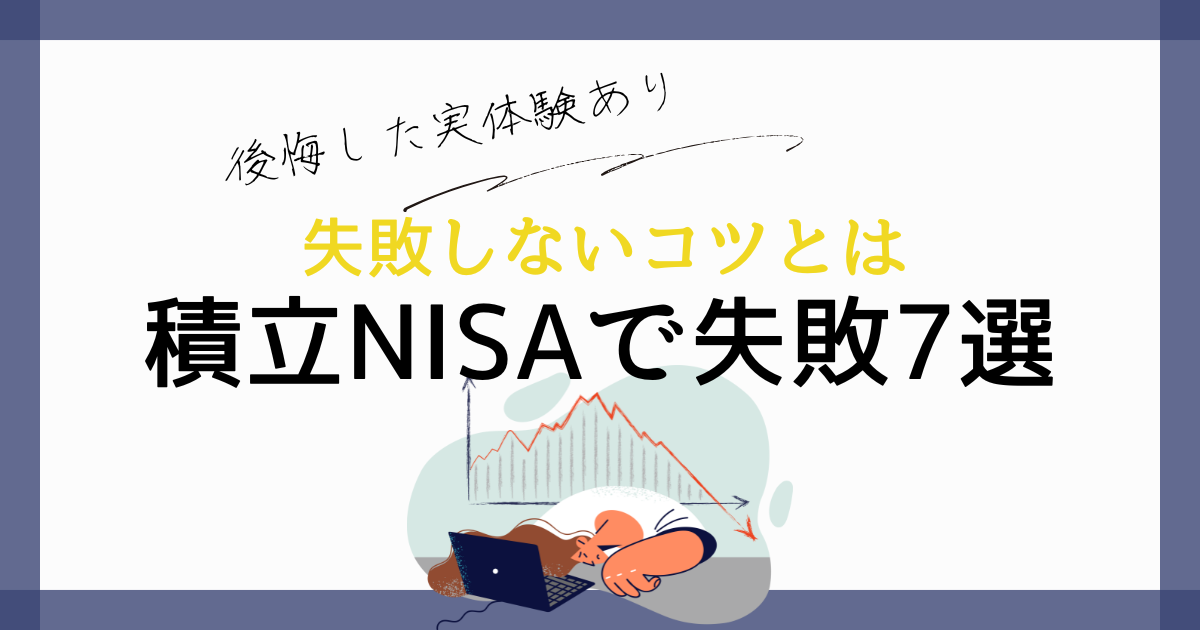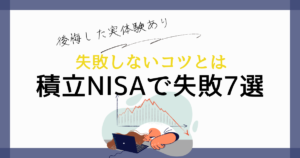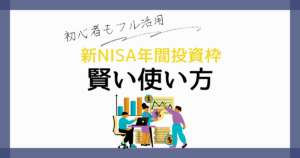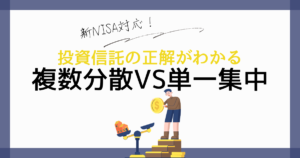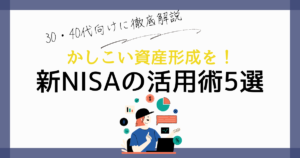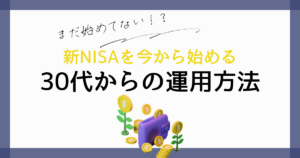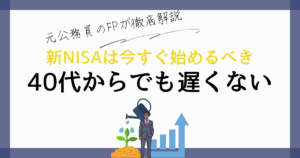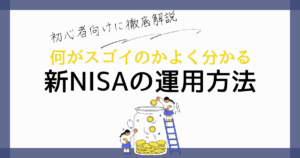「積立NISA、やってみたけど後悔してる…」
SNSやブログでそんな声を見かけて、不安になっていませんか?
実は私も最初は知識ゼロで始め、信託報酬の高い商品を選んでしまったり、暴落に慌てて売ってしまったり…。
でもそこから投資の基本を学び、楽天証券とSBI証券で投資を継続。
今では資産が200万円以上増え、毎月の積立が安心に変わりました。
この記事では、積立NISAでよくある後悔や失敗パターンを具体例とともに解説しながら、
・なぜ失敗するのか?
・どうすれば後悔を防げるのか?
・初心者でも失敗しない選び方と続け方
これらについて、やさしく丁寧にお伝えします。
「これから積立NISAを始めたい」「すでに始めて不安…」という方は、この記事を読むことで安心して投資を続ける自信が持てるようになります。
 筆者
筆者結論から言えば、積立NISAで後悔しないためには、「正しい知識」と「無理のない継続」がカギ。
あなたの不安を希望に変えるヒント、ぜひ受け取ってください。
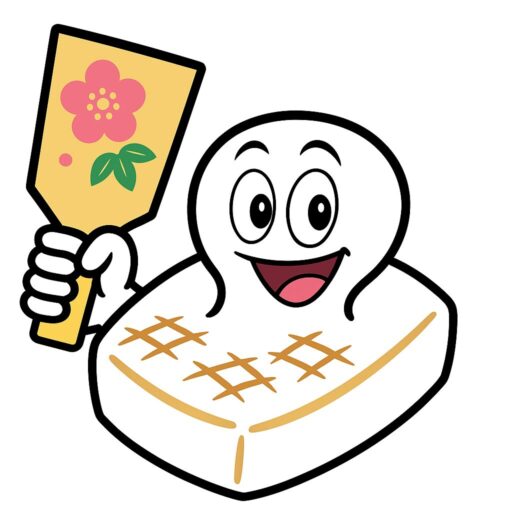
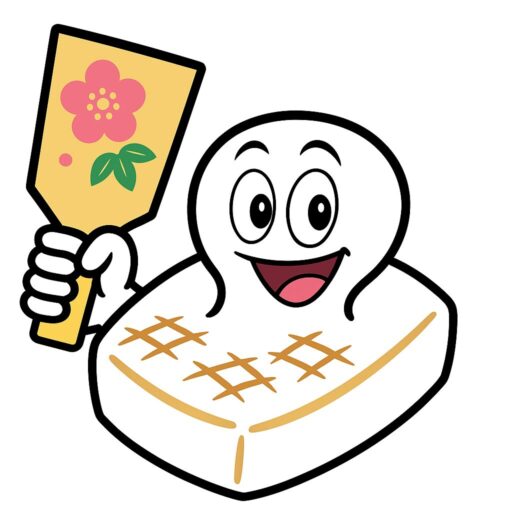
はごもち
- 元役所勤務
- FP技能士2級
- 現ウェブライター
- iDeCoで6年運用中
- 旧NISAで元本約2倍
- 新NISA満額めざし積立て
おことわり
この記事は、ぼく自身が学んだことや調べたことをまとめたもので、あくまでも情報提供が目的です。
特定の商品や投資手法をすすめたり、売買を勧める意図はありません。
できる限り正確な情報をお届けできるよう心がけていますが、内容の正確性・完全性などは保証できません。
もし、この記事の内容を参考にして損失が出たとしても、責任は負えませんのでご了承ください。
投資は最終的にご自身の判断と責任で行うものです。焦らず、じっくり考えてから決めてください。
よくある積立NISAの後悔・失敗6つのパターン
知識不足で商品選びを誤り後悔|信託報酬の高い投資信託を選択してしまった
信託報酬が高い商品を選ぶと、将来の利益が減ってしまいます。
信託報酬とは「投資信託を運用してもらうための手数料」です。
この手数料が高いと、利益からどんどん引かれてしまいます。
たとえば、同じ年5%の利回りで20年投資した場合、
| 商品A(信託報酬1.5%) | 商品B(信託報酬0.1%) |
|---|---|
| 約186万円の利益 | 約265万円の利益 |
→ 約80万円も差がつくという試算があります(※金融庁「つみたてシミュレーター」参照)。
初心者ほど「信託報酬の低い商品(年0.2%未満)」を選ぶことが成功の第一歩です。
市場の暴落でパニック売り|途中解約して損失を確定するタイミングのミス
暴落時に売ると「損失確定」で本当に損をしてしまいます。
相場は上がったり下がったりを繰り返しています。
特に長期投資では、「下がったから売る」より「持ち続ける」ことが大切です。
※金融庁HPでも「20年間運用すると元本割れのリスクはほぼゼロ」※とされています。
金融庁が公表する長期・積立・分散投資のシミュレーションによると、世界株式と国内債券を組み合わせたポートフォリオを20年間保有した場合、過去データでは元本割れしたケースは約0.4%(250ケース中1件)にとどまっています。
※あくまでも過去の実績に基づく試算で、将来を保証するものではありません。
株式投資はジェットコースターのようなもの。
途中で降りたらケガをするけど、最後まで乗っていればちゃんと安全にゴールできます。



下落時は「売らずに耐える」ことが将来の利益につながります。
積立金額を高く設定しすぎ生活が苦しくなった失敗
積立金額は“無理のない範囲”で設定するのが鉄則です。
毎月の積立が家計を圧迫すると、途中でやめたくなってしまいます。
積立NISAは「続けること」に意味があります。続けられなければ効果は出ません。
住友生命のデータでも、日本人の平均貯蓄額は月約3万円ほどとなっており、
この範囲内での積立設定が理想的です。
重すぎるリュックを背負って山登りをしたら、途中で疲れて引き返したくなります。
最初は軽めの荷物(少額積立)でスタートしましょう。



最初は月1〜3万円から。生活に無理のない金額で始めるのが続けるコツです。
投資を途中でやめてしまったことへの後悔|コツコツ継続できなかった
積立NISAは「コツコツ続ける人」ほど成功します。
投資の大きな武器は「複利効果(利益が利益を生む仕組み)」です。
でも、それは時間をかけて続けた人だけが得られるものです。
金融庁によると、20年積み立てた人は、運用益の伸びが飛躍的に増えるというデータがあります。
木を育てるのと同じで、水やりを毎日やめずに続けてこそ、大きな木になります。
途中でやめると、まだ育ちきらないうちに枯れてしまうんです。



積立NISAは「習慣」にすれば負担は減り、結果は大きくなります。
元本割れが怖くリスクを取れずチャンスを逃した後悔
リスクを避けすぎることが最大のリスクです。
確かに投資には元本割れのリスクがあります。
でも、何もしないことにもリスクがあります。それが「インフレ」です。
総務省統計局のデータでは、日本の物価は20年間で約15%上昇しています。
つまり、現金のままでは価値がじわじわ減っていくのです。
怖いと感じるなら、まずはリスクの少ない投資信託から始めるのがおすすめです。
証券口座・金融機関の選択ミス(商品の少ない銀行で開設して後悔)
最初の「証券会社選び」が積立NISAの成否を分けます。
銀行口座では、選べる投資信託の数が限られていたり、手数料が高いことも。
一方、楽天証券やSBI証券などのネット証券は、低コスト商品が豊富で使いやすいです。
| 比較項目 | 銀行NISA | 楽天・SBI証券(ネット証券) |
|---|---|---|
| 商品の種類 | 少ない | 豊富(2,000本以上) |
| 手数料 | 高めのものが多い | 低コスト中心 |
| 使いやすさ | 書類手続き多め | スマホ完結で簡単 |



迷ったら「楽天証券」または「SBI証券」で開設しておけば間違いありません。
👉 楽天証券の新NISA開設方法はこちら
👉 SBI証券の新NISA開設方法はこちら
\楽天経済圏の人は迷わずこちら /
\ 実績と人気で選ぶならこちら/
「積立NISAはやめたほうがいい」と言われる8つの理由~積立NISAのデメリット~
元本保証がなく値動き次第で元本割れリスクがある
投資に絶対はなく、元本割れのリスクもあることを理解してきましょう。
積立NISAは「投資」であるため、預金のように元本が保証されているわけではありません。
価格が下がれば、元本を下回るリスクもあります。
とはいえ、金融庁の調査では「20年間積み立て投資を続けた場合、元本割れの可能性は1%未満」と報告されています※。
模試で思ったより点数が悪いこともありますが、コツコツ続けた人が本番に強いのと同じです。
一度のミスで投げ出さなければ、トータルでは成果につながります。



短期の変動に焦らず、長期目線で淡々と続けることが大切です。
非課税運用期間は無期限だけど、途中解約には注意
新しいNISA制度(2024年~)では、つみたて投資枠も成長投資枠も非課税期間が無期限になりました。つまり、保有し続けるかぎり、売却益や分配金に税金はかかりません。
途中で売却(解約)することもいつでも可能です。ただし、一度売却すると、その年の非課税枠は使い切った扱いとなり、売却後に再投資しても枠が復活することはありません。
そのため、「数年以内に使う予定のあるお金」には向かない制度といえます。非課税のメリットを最大限活かすには、長期で持ち続けられる資金を使うのがベストです。
試験直前に参考書を読み始めても、なかなか成果は出ません。時間をかけて地道に勉強した人ほど、本番で力を発揮できますよね。NISAも同じで、「じっくり保有」するほど結果が出やすい仕組みです。
損益通算や損失繰越ができず、赤字でも税優遇を受けられない
つみたてNISAで損が出ても、税金の優遇は受けられません。
通常の証券口座では、損失を出した場合に「損益通算(利益と損を相殺)」や「損失繰越(翌年以降に損を繰り越す)」が可能です。
しかし、つみたてNISAではこれができません。



損をしたときに備えて、リスクの低い商品を選ぶことが重要です。
投資対象が投資信託のみで選択肢が限られる|個別株やETFは利用不可
つみたてNISAは「投資信託」しか買えません。
制度上、対象商品は金融庁が認めた投資信託(主にインデックス型)に限定されています。
個別株やETFは新NISAの「成長投資枠」でしか買えません。
「教科書だけで勉強しなさい」と言われて、参考書やYouTube解説が使えないような状態です。
ただし、教科書だけでも基礎力は十分につきます。



つみたてNISAは、「王道・安定志向」の資産形成に向いています。
年間の非課税投資枠が少なく、大きな資産形成には時間がかかる
つみたてNISAだけで数千万円を貯めるのは時間がかかります。
新NISAのつみたて投資枠では年間120万円まで。
時間をかけて育てる制度なので、短期間で大きな利益を出したい人には不向きです。
難関大学を目指す受験生が、1か月だけの勉強で合格するのは難しいですよね。
でも、毎日コツコツ積み重ねれば、1年後には合格レベルに達することもできます。
投資も同じで、焦らず続けることが何より大切です。



積立NISAは、“ゆっくり着実に”お金を増やしたい人に最適な制度です。
分配金を受け取れない|再投資型のため現金収入が得られない
分配金を毎月受け取るタイプの投資ではありません。
つみたてNISAで選べるのは「分配金を自動で再投資するタイプ(再投資型)」の商品が中心です。
そのため、定期的にお金を受け取りたい人には合いません。



つみたて投資枠は、配当金より「資産全体の成長」を重視したい人に向いています。
一括投資ができず、相場急落時にまとめ買いすることができない
つみたてNISAは「一括で買う」ことができません。
制度上、月ごとの積立が前提となっているため、相場が大きく下がったときに“まとめ買い”ができないのがデメリットです。
模試の成績が悪かったからといって、一晩で全部の教科を詰め込むことはできないのと同じです。
毎日コツコツやるしかありません。



一括投資したい人は、新NISAの「成長投資枠」を併用しましょう
手軽に解約できてしまうため、短期でやめてしまう人もいる
「簡単にやめられる」からこそ、続ける意思が必要です。
つみたてNISAはスマホで簡単に解約できます。
その分、不安になったときにやめてしまう人が多いのです。
やる気が出ないときに「今日だけ休もう」とサボり、そのままやめてしまう受験生と同じです。
続けることが何より大事です。



長く続けるために、初めにしっかりとした目的をもって始めましょう。
積立NISAが向いていない人・おすすめしないケース6選
元本割れなど投資リスクを一切受け入れられない人
リスクがゼロでない以上、絶対安全を求める人には不向きです。
つみたてNISAは、元本保証のない「投資」です。
価格が下がる可能性はどうしても避けられません。
「1円も減ってほしくない」という人には、預金や定期預金が向いています。
サッカーでは、ロングシュートを狙えば相手にボールを取られるリスクがありますよね。
リスクをゼロにしようとしたら、ずっとパス回しだけでシュートが打てません。
ロングシュートを打つから相手のディフェンスラインが下がって攻めやすくなったり、敵に当たってゴールになる可能性だってある。



少しでも「お金が減るかも」と不安なら、リスクをとらない選択肢を選ぶのが正解です。
近い将来に大きな支出予定があり長期間資金を拘束できない人
「5年以内に使う予定のお金」は積立NISAに向いていません。
積立NISAは非課税で20年間運用することが前提です。
途中で売却しても構いませんが、その分、非課税のメリットを十分に活かせなくなります。



留学・住宅購入・結婚などで数年以内に使うお金は別に管理しておきましょう。
商品選びや運用の勉強をしたくない人(投資に関心が薄い人)
投資にまったく興味が持てない人には、向いていません。
つみたてNISAは「ほったらかし」でOKとよく言われますが、最低限の基礎知識は必要です。
興味がまったくないと、商品選びや確認作業が面倒になり、失敗につながることも。
サッカーに興味がない人が、ルールを知らずに試合に出ても動けませんよね。
プレーするには、ルールの理解が欠かせません。



投資に関心が持てないうちは、無理に始めない方が安心です。
老後資金など明確な目的がなくなんとなく始めようとしている人
「何のためにやるのか」がないと継続しにくくなります。
目的が明確でないと、相場が下がったときに「やめようかな」と迷いやすくなります。
「老後資金」「教育資金」など、ゴールがある人ほど続けられます。
ゴールの場所が分からないマラソンコースを走っても、どこに向かえばいいか分からず不安です。
ゴールがハッキリしているから、迷わず走ることができます。



始める前に「このお金は何のため?」を自分に問いかけてみましょう。
iDeCoなど他の制度のメリットを活用せずバランスを考えていない人
積立NISAだけでなく、他の制度とのバランスも大事です。
iDeCoや企業型DCには、節税メリットや強制力があるという特徴があります。
特に「老後資金」はiDeCoと組み合わせると効果的です。



つみたてNISAとiDeCoは、どちらも活かすことで資産形成のゴールに近づけます。
短期で大きな利益を狙う投資スタイルの人(長期積立では物足りない人)
つみたてNISAは「コツコツ型」。短期での爆益は期待できません。
つみたてNISAの目的は、時間をかけてゆっくり資産を育てることです。
3か月で2倍などのハイリターンを求める人には不向きです。
得点王になりたいからといって、1試合で10点取ろうとしても無理があります。
毎試合1点ずつ積み上げる選手の方が、最終的に記録を残します。



「時間をかけて育てる」のが積立NISA。短距離勝負の人は別の投資を検討しましょう。
積立NISAで後悔しないためのコツ・対策7選
生活に支障のない余裕資金で始め、毎月の積立額は無理のない範囲に設定する
無理のない金額でコツコツ続けることが、成功の近道です。
積立NISAは「長く続ける」ことが重要な制度です。
最初から月5万円など無理をしてしまうと、家計が苦しくなり、途中でやめる原因になります。
金融庁の資料でも、月1〜3万円の積立が一般的とされています。
家計に余裕がないのに、いきなり高級外食ばかりすると家族の暮らしが破綻してしまいます。
毎日の食費を圧迫しないように、予算内でおいしいごはんを楽しむ感覚です。



「生活を守れる金額」で設定し、まずは続けることを最優先にしましょう。
相場の一時的な暴落・暴騰に動じず、長期的な視点で運用を続ける
相場が下がっても“慌てず続ける”が成功の秘訣です。
株価が下がると「損している気分」になりますが、売らなければ損は確定しません。
むしろ、安く買えるタイミングなので「仕込みどき」とも言えます。
長期保有することで、リスクは年々減少する傾向があります(金融庁より)。
恋人とケンカしても、すぐに分かれてしまうのではなく、話し合いながら解決していくことで関係を築いていくことができますよね。
相場との付き合いも、長く続けるほど信頼関係が育ちます。



相場に一喜一憂せず、「淡々と続ける」ことを大切にしましょう。
低コストで実績のあるインデックスファンドを中心に商品を選ぶ(信託報酬を重視)
運用コストが低い商品を選ぶことが、資産を増やす近道です。
信託報酬(=手数料)が1%違うだけで、20年後には数十万円もの差になります。
金融庁や専門家は、信託報酬0.2%未満の商品を推奨しています。
毎月の生活費で、電気代や水道代を少しでも節約すれば、家計がぐっと楽になりますよね。
運用コストも同じで、目に見えない“出費”を減らすことが大切です。



人気の「eMAXIS Slim」シリーズなど、信託報酬が安い商品を選びましょう。
定期的にポートフォリオや運用状況を点検し、必要に応じて調整する
「年に1回の見直し」が継続のコツです。
投資環境や自分のライフスタイルは変化していきます。
定期的に見直すことで、積立金額や商品が今の自分に合っているかを確認できます。
車で家族旅行をしているときも、ガソリンやタイヤの点検をすることで安全に走れますよね。
投資も同じで、途中の点検が安全な資産形成につながります。



毎年お正月や誕生日など「決まった時期」に運用の健康診断をしてみましょう。
SNSや他人の意見に流されず、自分の投資方針を貫く
「自分の考え」で選ぶことが失敗しない最大のポイントです。
SNSでは「この商品で儲かった!」「やめた方がいい!」など、さまざまな意見が飛び交っています。
ですが、人それぞれ投資の目的や収入、家族構成が違うので、誰かの成功が自分にも合うとは限りません。
他の家庭が「毎日外食してるからうちも」と真似したら、お金が足りなくなるかもしれません。
自分の家には自分のルールがあるのと同じです。



「うちはうち、よそはよそ」。自分の投資スタイルを大事にしましょう。
途中で不安になってもすぐ解約せず、積立停止や一時放置で様子を見る
「解約=やめる」ではなく、「止める」だけでもいいんです。
不安になったときにすぐ解約してしまうと、今まで積み上げた非課税のメリットを手放すことになります。
代わりに「一時停止」するだけでもOK。状況を見て再開できます。
家族でちょっとしたトラブルがあっても、距離を取るだけで関係を守れることがあります。
いきなり離婚するより「冷却期間」をおくようなイメージです。



迷ったらまずは積立の一時停止。「続ける道」をなるべく残しておきましょう。
iDeCoも検討し、自分に最適な資産形成方法を選ぶ
制度は組み合わせて使うと、さらに効果が高まります。
つみたて投資枠だけでなく、成長投資枠やiDeCoにはそれぞれ特徴があります。
たとえば、iDeCoは老後資金を“強制的に貯める仕組み”として優秀です。
家族で家事を分担すると、一人の負担が減りますよね。
資産形成も、制度を分担させるとバランスよく育てられます。



つみたてNISAにこだわりすぎず、他制度も活用して“家計のチーム力”を上げましょう。
よくある質問(Q&A)
まとめ|「後悔しないNISA」にするには、正しい知識と無理のない設計から
- 知識不足・焦り・無理な金額設定が後悔の原因になる
- 元本割れリスクを理解し、長期視点で運用する
- 続けることが最大の勝ちパターン。途中停止も活用しよう
- 口座は楽天証券 or SBI証券がベスト。商品選びも手数料重視で
積立NISAで後悔する人には共通点があります。
それは「よくわからないまま始めてしまった」「無理な金額設定をした」「相場の上下に振り回された」など、“準備不足”と“継続の工夫”が足りなかったという点です。
でも安心してください。
積立NISAは、正しい知識を持ち、ムリなくコツコツ続けるだけで、誰でも将来の安心につながる制度です。
信託報酬の低いインデックスファンドを選び、家計に負担のない金額で始め、焦らずに続けること。これが、後悔しない最も確実な方法です。
始めるのが遅くても、気づいた「今」がいちばん早いタイミング。
この記事が、あなたの不安を解消し、「やってよかった積立NISA」につながる一歩になればうれしいです。
未来の安心は、今日の小さな行動から。
自分のペースで、一緒に前に進んでいきましょう!